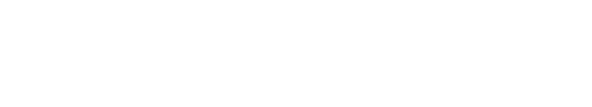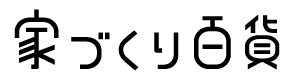何気ない日常のなかに、
小さな喜びや幸せを
感じられる木の家
家は完成してからが本当のはじまりです。
毎日の暮らしをを受け止めながら、住まう人の人生が豊かになるような
そんな家を建てたいとマルトは考えています。
施工事例
マルトがご提案をさせていただいた木の家の事例のご紹介です。
どの家もお客様の暮らしに寄り添う家となっています。
注文住宅だからこそ、それぞれ違う居心地の良い木の家になりました。
私たちの考え
「家を建てる」という言葉から何を想像しますか?
「リビングは最低でも8畳」「書斎が欲しいな」「坪単価いくらで建つんだろう?」
これらは大切な事ではありますが「家を建てる」という行為の表面的な部分でしかありません。家とは人が生まれて命を終えるその日までの、日々の暮らしや成長の歴史の舞台です。つまり家族の暮らしを支える根幹なのです。
健康で暮らすことを助け、安心・安全な空間であり、長く住み繋いで行けることが、家族の暮らしを守り支える家づくりの基本だとマルトでは考えています。
会社案内
祖父・父から受け継いだ「樹を活かす」仕事。木を育てることから始まり、
三代に渡ってこの地で仕事を継いできたことがお客様の暮らしを守り、
地域への貢献にもなり、次の世代へとつながっているのだと感じています。